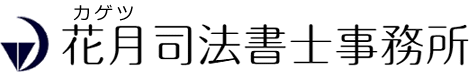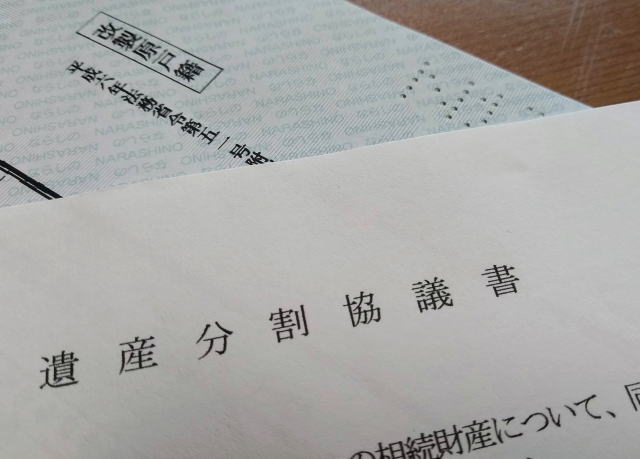親が亡くなり親名義の土地を相続する際、登記簿を取得して見ると、甲区の登記の目的の欄に「条件付所有権移転請求権仮登記」、「原因 年月日売買(条件 農地法第3条の許可)」と記載されているが、どういう意味?
所有権が移転する登記が「仮」として登記されている、ということは今後、この土地の所有権は第三者に移転するのか?
「仮」と書かれているので、そんなに気にする必要はないか?
「仮」という文字で軽い意味に思われる方もおられますが、実は場合によってはその後に続く登記を吹き飛ばすほどの力もあり軽視することはできません。
相続する土地に仮登記がされている場合にどう対処するか、まず、仮登記について説明し、その後に対処方法をご説明します。
仮登記の種類
仮登記には、1号仮登記、2号仮登記と呼ばれる2種類があります。
1号仮登記は、既に権利変動は生じ(権利は相手に移転している)所有権移転登記ができる状態にあるが、書類の不備等の問題ですぐに登記申請ができない場合に、変動した権利を確保するために、とりあえず「仮」としてする登記です(登記して公示する)。
「所有権移転仮登記」「原因 売買」と記載されている場合、それは1号仮登記になります。
売買が成立して所有権(物権)は売主から買主に移転していますが、書類が揃わず登記申請できないようなケースに仮登記をします。
2号仮登記は、権利変動はまだ生じていないが変動させる請求権は成立(売主と買主間の約束の成立)したので、それを確保するためにする仮登記です。
今回は、仮登記でよくみられる「所有権移転仮登記」と「所有権移転請求権仮登記」についてご説明します。
所有権移転仮登記
1号仮登記である所有権移転仮登記は、既に物権は変動している(所有権は買主に移転している)が、手元に移転登記に必要な書類(登記識別情報等)が足りないために移転登記がすぐにできないようなとき、その書類がなくてもできる仮登記をして順位を保全します。
※順位を保全する意味は下記「順位・権利の保全」を参照ください。
その後、書類が揃ったところで仮登記を通常の移転登記に切り替える登記をします(これを仮登記の本登記と言います)。
仮登記は通常の登記と同様に共同申請(売主と買主)で行いますが、売主(登記義務者)の承諾があれば買主(登記権利者)が単独で登記することもできます。
所有権移転請求権仮登記
所有権移転請求権仮登記は2号仮登記に分類されます。
まだ物権変動は生じていないが、物権変動を将来に生じさせる請求権は発生している場合や、期限や条件等が付けられてその期限が到来したり、条件が成就した場合に物権が変動するようにした場合、その請求権を保全するために仮登記として登記します。
例えば、売買契約を締結したが売買代金の支払いが後日の場合、普通、所有権移転登記は代金支払いと同時に行われます。
この場合、「条件付所有権移転仮登記」「原因 年月日売買(条件 売買代金完済)」として仮登記します。
売買契約はしたのでその旨の仮登記をし、正式に移転登記(本登記)をするのは売買代金が全額が支払われた時になります。
農地を売買する場合で、契約はしたがまだ農地法の許可が出てない時は、「原因 年月日売買(条件 農地法第3条の許可)」のように仮登記します。
仮登記の意味
仮登記がされる目的は、順位保全であり、権利保全にあります。
順位・権利の保全
民法177条に「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」と規定されています。
つまり、「登記をすれば第三者に対抗することができる」ことになるので、先に登記したものが勝つ事になります。
※「対抗」とは、自分の権利が認められることを意味します。
例えば、所有者AがBとCに二重に土地を売却した場合、Aから取得した当該土地のBとCの所有権は、相容れない衝突する権利になります。
BC双方、自分がAからこの土地を買った、この土地は自分のものだ、と主張するでしょう。
この場合、177条に従えば、先に登記した者が当該土地の所有者になる、ということになります。
このように登記は絶大な効力を持ちますが、何らかの事情で登記がすぐにできない場合、登記の順位及び権利を保全する必要があり、それが仮登記になります。
登記簿には、「順位番号」という欄があります。
登記をすると、この欄に1,2,3と順位が付されていきます。
順位1番で所有者Aと記録されている土地の登記簿に、順位2番で「所有権移転」「所有者B」と記録されたら、Bは「対抗力」を得たことになります。
仮に同じくAから当該土地を買ったCがいても、Bが先に順位2番で登記をされているのでCは自分を所有者とするAからCへの所有権移転登記をすることができません。
しかし、Bが書類の不備等で「順位2番」で「所有権移転登記」をすぐにすることができない場合はどうするか。
書類が揃うまで登記をしないでいると、その間にCに「順位2番」で「所有権移転」の登記をされるおそれがあり、先に登記されるとCが所有権を取得することになります。
そこで、Bができることは、「順位2番」を確保するために書類が不備でもできる「所有権移転(請求権)仮登記」を「順位2番」でします。
「順位2番」でされた登記は仮登記であり所有権移転登記ではないので、Cさんは「順位3番」で自己を所有者とする「所有権移転」登記をすることは可能です。
しかし、その後、Bが順位2番の仮登記の本登記をすると(仮登記をもとに正式に所有権移転登記をする)、順位2番のBの所有権と順位3番のCの所有権が衝突するので、下位順位3番のCの所有権登記は抹消されることになります。
これが仮登記の威力です。
「仮」ではありますが、遅れる登記を吹き飛ばす力を持っています。
相続する土地に仮登記があったら
以上が「仮登記」の効果です。
仮といえども無視できない事をご理解いただけたと思います。
では、相続する土地に仮登記が付されている場合はどうするか。
仮登記があっても相続登記は可能ですが、仮登記があるとその後に登記をしても権利がぶつかる場合は抹消されてしまうおそれがあります。
また、仮登記がついたままでは売却が難しくなります。
そこで、仮登記が抹消できないかを検討します。
仮登記の抹消
仮登記が昭和や平成初期の何十年も前に設定されたものであれば、仮登記の権利者は本登記をする気がない、抹消されないまま残っているだけのケースが多々あります。
このような場合、権利者にとっても意味がないので、抹消登記に協力してくれる場合があります。
基本的に登記の抹消は、登記権利者(仮登記の名義人)と義務者(設定者)との共同申請になるので、権利者に事情を話して理解してもらい、共同で抹消申請をします。
ただし、権利者にとっては何のメリットもないので、協力をお願いするにあたっていわゆる「ハンコ代」が必要になることもあります。
単独で抹消
義務者(土地所有者)は、単独でも抹消申請することができます。
この場合でも申請に権利者の承諾書(印鑑証明書も要)が必要になりますが、共同申請よりは負担が少ないので協力をお願いしてみましょう。
裁判による抹消
古い仮登記だと権利者と連絡をとるのも難しくなります。
権利者に相続が発生していて相続人が多数になっていれば、全員から協力を得るのは難しいでしょうし、相続人の中には行方不明で連絡をとることさえできないというケーズもあり、対応に時間も費用もかなりかかってしまいます。
このような場合は、裁判をして抹消することを検討します。
付されている仮登記が「所有権移転請求権仮登記」であれば、当事者間において相手側(権利者)は義務者に所有権を移転することを請求できる権利(約束)を得ていることを意味します。
原因が「売買予約」であれば、権利者(買主)は売買に関する予約を完結する権利(予約完結権)を取得しますが、これは債権(当事者間の約束事)なので、10年(2020年民法改正後に成立した債権であれば5年)で時効により消滅します。
この時効期間が完成していれば、仮登記の抹消を求める訴訟を起こし、勝訴判決を得られれば単独で抹消できます。
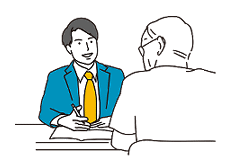
初回のご相談は無料です。
ご相談の予約はこちら
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)
※電話でのご相談には対応しておりません。