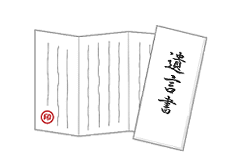
遺言書は、相続人間の相続争いを防止するための有効な手段です。
遺言書の内容に不満があっても、その内容通りに従う他なく、無用な争いを防ぐことができます。
遺言書を書く場合、遺産を相続人に渡したい場合は「○○に相続させる」と書き、相続人以外の者に渡したい場合は「〇〇に遺贈する」と書きます。
「相続させる」と書かれた遺言書があれば、登記手続きも他の相続人や遺言執行者に関係なく単独で行うことができます。
対して、「遺贈」の場合は、登記手続きも相続人全員(遺言執行者がいればその者)と協力して行わなければいけません。
このように遺言書の「相続させる」という文言の効力は強く、相続人に遺産を引き継ぐ場合によく使われますが、プラスの面もあればマイナスの面もあるので、遺言書を作成する場合、よく理解した上で使用することが大切です。
「相続させる」遺言書
相続させるという文言はよく遺言書に使われます。
遺言書の文言について裁判で争われてきましたが、相続人に対して「〇〇を相続させる」とする遺言書は最高裁で絶対的効力が認められ、遺言書の効力が発生する、つまり、遺言者が死亡すると同時に対象となった相続財産は指定された相続人が自動的に(何の手続きもなしに)所有権を取得すると判示されました。
※従前は何もしなくてもいかなる者に対して対抗(主張)できるとされていましたが、民法が改正され、「法定相続分を超える部分」については登記をしないと第三者に対抗(主張)できないとされています。
これにより、以後、特定の相続人に相続財産を渡したい場合、「相続させる」という文言が使われるようになりました。
ただし、よく使われるようになった「相続させる」という文言もメリットだけでなくケースによってはデメリットになることもあります。
遺言書でこの文言を使うときは、両面を考慮した上で使うことが大切です。
メリット
相続させる遺言は、効果が強力なので手続きを単独で行う事ができることがメリットになります。
遺産分割協議に基づく相続登記だと、相続人全員の承諾、実印、印鑑証明書が必要になりますが、相続させる遺言書に基づく登記手続きに他の相続人の関与は必要ありません。
所有権は相続発生と同時に取得しているので、手続きは単独で行うことができます。
登記申請書に添付する書類も、被相続人と指定相続人の戸籍謄本、指定相続人の住民票、遺言書のみです。
※法務局に保管されていない自筆遺言証書は改訂裁判所の「検認」手続きが必要です。
他の相続人の戸籍謄本は不要ですし、被相続人に関しても除籍謄本のみで生まれてからの戸籍(改製原戸籍)を取得する必要はありません。
このように、他の相続人と一切接触することなく登記手続きができるので、相続争いを回避する有効な手段となっています。
また、対象土地が農地であれば、「相続させる」とすれば、農地法に基づく許可も不要になります。
相続人に対して「遺贈する」としても有効ですが、先に述べた最高裁判例は適用されないので、手続きには他の相続人の協力が必要になり、また、農地法の許可も必要になります。
デメリット
相続させる遺言にも、その強力な効果ゆえのデメリットがあります。
望まない不動産の取得
相続させる遺言で、指定された相続人は遺言者が亡くなると自動的に特定不動産の所有者になります。
取得した者が当該不動産の取得を望んでいれば良いですが、望んでいなければどうでしょうか?
相続人がA、Bのお子さん2人で「甲土地はAに相続させる」とする遺言書があり、Aは甲土地を望まないがBが望んでおり、AもBが取得することに賛成している場合、どのように処理するかが問題になります。
遺言書がなければ、AとBで遺産分割協議を行いBが相続するように決めれば故人からB名義に直接移転登記できますが、「相続させる」遺言があると、先に述べた最高裁の判例に従い故人が亡くなると同時に甲土地はAの意思に関係なくAが所有権を取得することになります。
Bが取得するには、基本的に一旦Aに相続登記した後に、贈与等を原因としてBに移転登記することになり、2回の必要な上、税金面で大きな負担が発生します。
相続させる遺言の内容と異なる遺産分割協議を行い、それに基づいて相続登記をするとする考え方もありますが、法的根拠が確立されておらず、その方法は不透明な状態にあります。
指定された相続人がどうしても不動産を相続したくない場合、相続放棄により不動産以外の遺産も放棄することになります。
このような点を気を付ける必要があるでしょう。
遺留分
各相続人には、相続人として最低限相続できる割合が権利として認められており、これを「遺留分」と言います。
遺留分は遺言者も否定することはできません。※否定するには「相続人の廃除」等の特別な手続きが必要です。
遺留分を侵害するような遺言書を作成すると、後日、相続人間の紛争の原因になってしまうので注意が必要です。
例えば、相続人が子供であるA、Bの2人であれば、各相続人の遺留分は4分の1になります。
このケースで「甲土地はAに相続させる」とする遺言書がある場合、甲土地の価値が全相続財産の4分の3以下であれば、Bは残りの4分の1を遺留分として取得できますが、4分の3を超えるときはBの遺留分を侵害している状態になります。
遺留分は権利なので、Bが遺留分の取得を主張しなければ問題ありませんが、主張すればAは遺留分に相当する金銭を授与しなければいけません。
金銭が無ければ甲土地を売却して工面する、ということにもなりかねません。
また、金銭があったとしても、遺留分を計算する上で紛争になることが多いです。
遺留分を計算するには相続財産全部が算出しなければいけません。
預貯金のように金額がはっきりしているものは良いですが、土地のような不動産の算定は簡単ではありません。
Aはできるだけ算定額を低くくしたいでしょうし、逆にBはできるだけ高く算定したいでしょうから、ここで意見が合わず紛争になるおそれがあります。
よって、こうならないように、ある程度、余裕をもって遺留分を考慮した遺言書の作成が必要になります。
