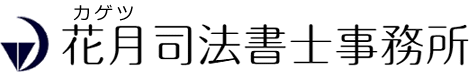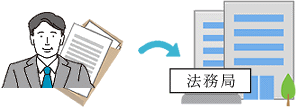相続登記

全ての不動産について登記簿が作成され、法務局で管理されています。
不動産を所有されている方が亡くなられると、当該不動産を相続で取得した方を新たな所有者として、登記簿に記録するための手続(相続登記)が必要になります。
現時点では相続登記は義務ではなく過料もないので相続登記を放置されている方もおられますが、令和6年4月1日から相続登記をすることが法律で義務となります(違反には過料あり)。
令和6年4月1日以降は、遡って全ての不動産が相続登記義務の対象となるのでご注意下さい。
相続登記費用
相続登記をする場合、必ずかかる費用として登録免許税(法務局に支払い)、申請書に添付する必要書類の発行手数料(役所に支払う)があります。
司法書士に申請をご依頼される場合は、上記の費用に司法書士報酬が発生します。
司法書士にご依頼されると、申請書の作成、必要書類の収集、作成、申請、権利証の取得まで全ての手続を任せることができます。
相続登記の重要性
登記簿に記録することは、当該不動産の所有者が自分であることを公示し所有者としての権利を確定するために重要です。
「この不動産の所有者は私です。」と公に示すことで、登記後に当該不動産に対して所有権とぶつかる権利を主張する者に対抗力を得ることができます。
「対抗力」とは、ぶつかる権利を主張する者に勝つ力です。
不動産に関して所有権をはじめ何らかの権利を取得するとき、この「対抗力」を得るために登記をすることはとても重要になります。
「対抗力」は、相続して所有権を取得した方だけでなく、以外の人も同様に登記をすることで得ます。
つまり、相続した方が相続登記をする前に、他の者が所有権とぶつかる権利を先に登記したら、その権利は相続により所有権を取得した者に勝つ、ことになります。
このように、「登記」は自分の権利を確保するためにとても重要な手続きです。
相続登記を放置した場合のトラブル
相続登記をせずに放置していると、いずれ相続登記をするときに非常に面倒であったり簡単にはできなくなってしまうおそれがあります。
事例:
母A名義の家に長男B家族が同居している。
Aには他に嫁いだ長女Cがいる。
Aが亡くな遺言書はない。
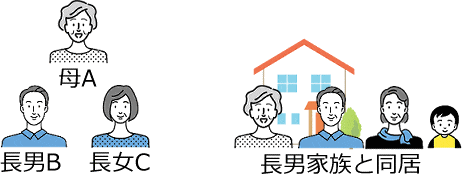
長男Bと長女Cで話し合って(遺産分割協議)母と同居していた長男Bが家を相続することに合意した場合、すぐに相続登記をすれば問題ありません。
登記には長女Cの実印が押印された遺産分割協議書と印鑑証明書が必要ですが、合意した直後なので押印や印鑑証明書の取得も協力的でしょう。
この遺産分割協議書と印鑑証明書があればBは単独で自己への名義変更のための相続登記申請ができます。
相続登記を放置していたら
相続人間で合意しているので安心して登記手続きを放置していると、その後に生じる状況の変化で大きなトラブルになるおそれがあります。
1.相続登記をしないうちに、長男Bが亡くなってしまった。
この場合、2つのパターンが考えられます。
長男Bと長女Cとで実印が押された遺産分割協議書を作成していたら、当該協議書を使うことができる可能性があります。
長男Bは亡くなっているので妻と子が相続人として申請することになります。
ただし、長男Bの印鑑証明書がなかったり(亡くなった方の印鑑証明書は発行できません)、長女Cの住所や実印が変わっていると別途手続きが必要になります。
協議だけで遺産分割協議書を作成していない場合は、長男Bの妻と子と長女Cとで改めて協議して遺産分割協議書を作成しなければいけません。
長男の妻は長女Cに現在の家・土地を自分たちの名義にするためにお願いすることになります。
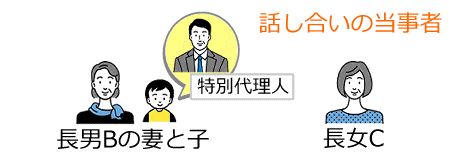
相続人である長男の子が18歳未満の未成年であれば、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになり時間も費用もかかってしまいます。
※親が相続放棄をすれば、親権者として子の代理人となることはできますが、代理は1人の子に対してだけで、お子さんが2人以上いる場合、2人目以降はそれぞれに特別代理人を選任する必要があります。
2.相続登記手続きをしないうちに、長女Cが亡くなってしまった。
BCの遺産分割協議書があれば上記と同様です。
なければ、長男Bは長女Cの夫と子と協議して遺産分割協議書を作成することになります。
長男はCの夫と子供に実印と印鑑証明書をお願いすることになります。
相続人である長男の子が18歳未満の未成年であれば、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになり時間も費用もかかってしまいます。
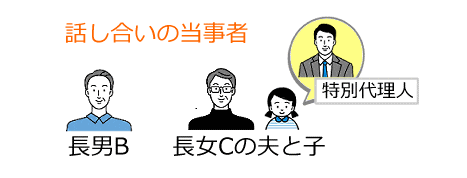
兄弟姉妹が亡くなると、その妻や夫、子が遺産分割協議の当事者になります。
財産に関しては血族間でも話しにくいことですが、配偶者の兄弟姉妹と実親でない配偶者の親の遺産分割について話し合うのはさらに話しにくくなってしまいます。
3.相続登記しないうちに長男B(又は長女C)が認知症になった。
認知症により判断能力が欠如しているので、B(又はC)は遺産分割協議をすることはできません。
この場合、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人と遺産分割協議をすることになります。
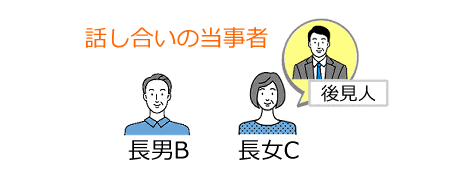
特に長女Cに後見人が就いた場合が問題になります。
遺産分割では後見人はCの利益になるかの視点で判断するので、長男が家全部を相続する内容を了承するかは分かりません。
他の方法としては、Cが亡くなるまで待ってCの相続人と遺産分割協議を行う方法もありますが、いずれにしてもすぐに登記をすることはできません。
 長期間放置していた相続登記をしようとした時、名義人が亡くなった日によっては家督制度が適用されることがあります。
長期間放置していた相続登記をしようとした時、名義人が亡くなった日によっては家督制度が適用されることがあります。
この場合、戸籍や相続人の調査に時間を要することになり簡単に手続きをすることができません。
詳細はこちら
相続登記への影響
相続手続を放置することで、その間に新たな相続が生じ、相続人が変わることで相続登記手続きにも影響してきます。
中間で生じた相続を省略できるか、できないかの判断や、申請書や遺産分割協議書の記載方法も異なってきます。
権利を失うことも
相続人間で協議して特定の相続人が遺産である不動産を相続するように決めても、相続登記を放置していると第三者の権利がついてしまうおそれがあります。
- 土地の所有者であるAさんが亡くなった。
相続人は子Bさん、Cさんの2人。
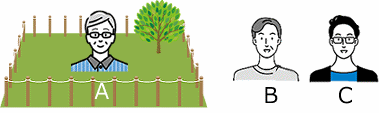

- B、Cさんは遺産分割協議をして土地はBさんが相続することで合意したが、Bさんはすぐ相続登記をしなかった。
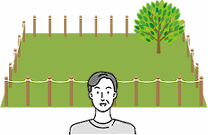

- Cさんには借金があり返済を滞納していて、債権者はCさんの財産から貸金を回収しようと検討。
債権者はCさんがAさんの相続人でありAさん名義の土地がまだ相続登記されていないことに着目して、この土地から回収しようと考えた。
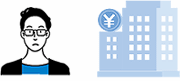

- 債権者は当該土地を法定相続分に従ってCさんに代わってB、Cさんの持分を各1/2として相続登記をした。
※債権者は差押えを目的としてB、Cさんに黙って単独でBCさんの相続登記(代位登記)をすることができます。
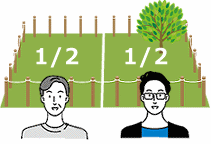

- 相続登記と同時にCさんの持分1/2を差押えた。
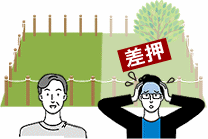
この場合、残念ながらBさんは「土地は全部私が相続しているので差押えを解除して下さい」とCさんの債権者に主張できません。
不動産の権利は先に「登記」をした者が勝ちます。
Bさんがすぐに相続登記をしていれば債権者は差押えすることはできませんでした。
債権者に差押えを解除してもらうにはCさんの借金の返済が必要になるでしょう。
上記のような場合、Cさんが相続放棄をしていれば、Bさんは相続登記をしていなくてもCさんの債権者に対抗することができます。
相続放棄の効果は相続開始時に遡るので、CさんはAさんの相続人でなくAさんの土地に何らの権利を有することがありません。
ただし、差押えの登記を抹消するには債権者の承諾書が必要になります。
承諾書をもらえなければ、裁判をして裁判所に抹消の許可をもらわなければいけなくなり大きな負担となってしまいます。
このことからも、「登記」は非常に重要なものとなります。
相続法改正でさらに相続登記が重要に
2019.7に相続法が一部改正され、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」とされました。
これは改正で大きく影響を受けるのが「相続させる遺言」です。
遺産分割協議をした場合、登記をする前に協議に反する内容の第三者の権利が登記されてしまったら、その登記の方が有効になってしまいます。
しかし、故人が特定の相続人に「相続させる」とする遺言書を残している場合、死亡と同時に確定的に特定の相続人が相続するので登記をしていなくても第三者に「対抗」できる(第三者が先に登記をしていてもその登記を否定できる)とされていました。
しかし、改正により「相続させる遺言」があっても登記しなければ、法定相続分を超える部分は登記を先にした第三者に対抗できないことなりました。
相続登記はできるときにすぐやる・・が重要
遺言書や遺産分割協議で相続することが決まっているのに相続登記を放置していると、その後の環境の変化、特に経済的変化でお金が必要になったりすると、いざ登記をする段になって内容を変えてほしい、遺産分割協議書に実印を押す押さない、印鑑証明書を渡さない等々でもめてしまうことがあります。
相続人が亡くなったり、認知症になったりすると決めた通りに登記することが簡単ではなくなります。
相続人が亡くなると、その相続人全員のハンコが必要になり人が多くなれば話しをまとめるのも難しくなります。
相続は「できる時にすぐやる」「登記をして権利を確定する」が重要です。
相続登記手続きの流れ
当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合、面倒で複雑な申請書の作成、必要書類の収集・作成、申請、権利証の取得までの全ての手続を丸投げすることができます。
ご相談予約から登記完了までの流れはこちらを参照下さい。
相続手続き丸ごとお任せプラン(遺産承継業務):
相続人・相続財産の調査、遺産分割、分配等の面倒な手続きを丸ごとお任せ下さい。
![]() 詳細はこちら
詳細はこちら
相続登記必要書類
相続登記手続きには、申請書類をはじめいろいろな書類が必要になります。
相続登記には「遺産分割協議書」や「遺言書」に基づいてする申請と法定相続割合に基づいてする申請があります。
申請方法によって提出書類も若干異なります。
全てに共通する必要書類
以下の書類は必ず必要なので取得する必要があります。
- 故人の除籍謄本・原戸籍
故人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍は必要になります。故人の現在の戸籍(除籍謄本)だけでは申請することはできません。 - 故人の住民票の除票(最後の住所地)
- 故人所有の不動産の固定資産評価通知書
![]() 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を1枚の書類にまとめることができる法定相続情報証明の詳細はこちら
戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を1枚の書類にまとめることができる法定相続情報証明の詳細はこちら
遺産分割協議書による相続登記申請

- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
相続人全員による協議で作成された書類に全員の実印が押印されたもの。
1人でも相続人が欠けると無効になります。
※司法書士に申請依頼される場合、通常、協議の内容に従って司法書士が遺産分割協議書を作成しますので、ご自身で作成する必要はありません。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 協議の結果、故人の不動産を相続すると決まった相続人の住民票
遺言書による相続登記

遺言書には自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)と公正証書遺言(公証役場で公証人が作成したもの)があります。
自筆証書遺言の場合、相続登記申請前に必ず家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
- 検認された自筆証書遺言、公正証書遺言
- 遺言書により相続する相続人の戸籍謄本及び住民票
※御覧のように遺言書があれば、必要書類も相続する当人のみのもので済み、他の相続人は関与しないので揉め事も回避することができます。
遺言書で相続人以外に遺産を渡す(遺贈)する場合
遺言書で相続人以外の第三者に遺産を贈与(遺贈)する場合、遺言執行者を指定しておくことをおススメします。
遺言執行者を指定しておくと、その執行者が全て遺贈の手続きをすることができますが、指定していないと相続人全員で手続きをしなければいけなくなります。
- 検認された自筆証書遺言、公正証書遺言
- 遺贈の対象となる不動産の登記識別情報(登記済証)=権利書
- 遺贈された方の住民票
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
遺言執行者が指定されていない場合は、上記4の替わりに相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要になります。
法定相続割合による相続登記
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
法定相続登記の問題点
協議で話し合いがつかなかった場合に、ひとまず法定相続割合に従って相続登記を、、、とするケースがありますが、おススメできません。
この登記には2つの問題があります。
1つ目は、保存行為として1人の相続人だけで申請できますが、その場合、登記識別情報(権利書)が申請した相続人に対してしか発行されません。
後に全員で土地を売却するとき、登記識別情報を持っていない相続人について司法書士による本人確認手続きか事前通知手続き(申請書提出後に法務局から送られてくる申請確認書面に実印を押して返送する)が必要となり、余分に費用や時間がかかってしまいます。
2つ目は、不動産が共有状態になってしまうことです。
土地を売却するとき、当然全員の承諾が必要になります。
自分の持ち分だけを売却することも可能ですが、買い手を探すことは難しいですし見つかったとしても安値で売ることになるでしょう。
土地全部を売ったときの価格の持ち分割合で売れることはまずありません。
法定相続での相続登記は、土地の買い手も見つかっていて登記後すぐに売却するような場合に有効です。
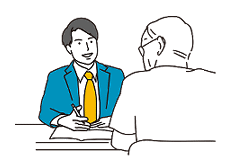
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)