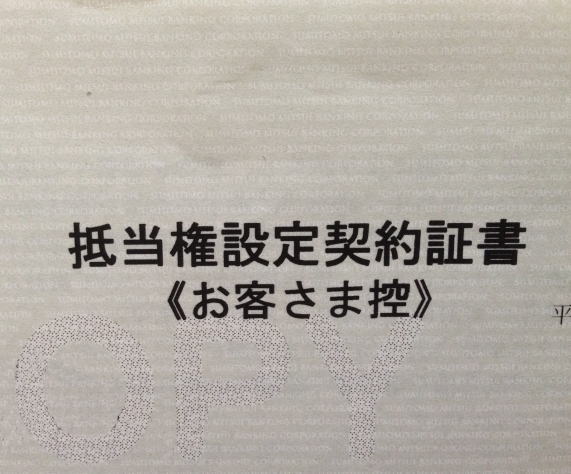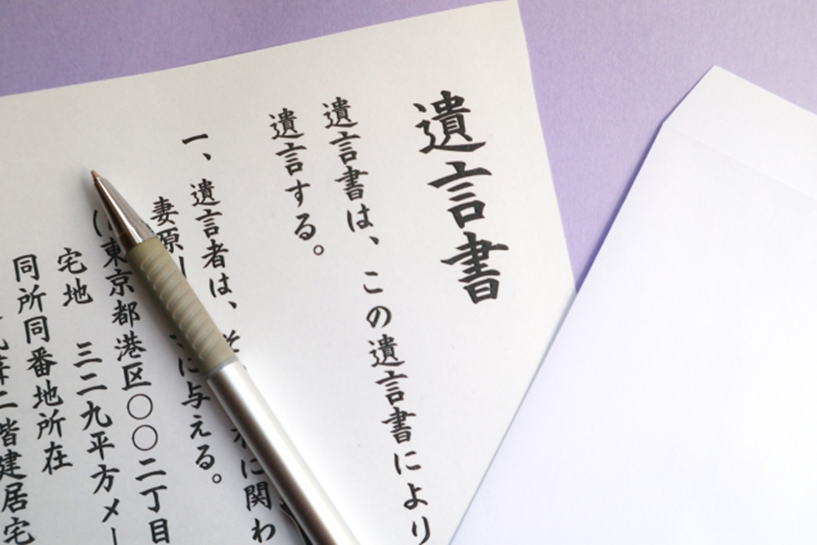
自分に何かあった後、相続で家族が争いにならないか心配、、と思われる方は多くいらっしゃいます。
遺言書がなければ相続人であるご家族で話し合って決めることになり、ここでもめてしまうことがあります。
揉め事を回避するには遺言書が最適で、自身の財産を各相続人にどうのように分割して相続させるか自由に指定することができます。
- 長男には家業を継いでもらうから他の相続人より多めに
- 妻の生活が心配なのでほとんどを妻に
- 次男とは絶縁状態なので一切渡さない
- 長女には結婚後、新居を建てる時に多額の援助をしているので遺産は他の子供に
上記のように家族ごとに様々な事情があり、遺産の分け方も異なるでしょう。
遺言書は作成者の意思で自由に各相続人に対してどのように遺産を分けるか書いて良いのですが、注意しなければいけないことがあります。
各相続人には法律で相続できる最低相続分が規定されています。
この最低相続分を「遺留分」と言います。
遺言書を書く際、この遺留分を意識して書かないと、もめないように書いた遺言書が原因でもめてしまうという皮肉な結果になってしまうおそれがあります。
ここでは、遺言書を書く際に注意しなければいけない「遺留分」について解説します。
遺留分とは
遺留分とは、故人(被相続人)とどのような関係であろうとも、相続人である以上最低限これだけは相続できる分として法律で規定されている相続割合です。
遺留分は法律で規定されていますが、必ず渡さなければいけないものではありません。
遺留分権利者の請求のもとに渡すことになります。
請求がなければ、渡す必要はありません。
※以下の相続人に遺留分は認められません。
相続放棄者、相続欠格者、相続廃除者(廃除者の子には認められます)、兄弟姉妹
遺留分の計算
遺留分は相続財産を半分にし、それに対する法定相続割合になります。
相続人が妻、子2人の場合、各相続人の遺留分は以下のようになります。
妻:相続財産x1/2x1/2=1/4
子:相続財産x1/2x1/4=1/8
※相続人が親(尊属)のみのときは、親(尊属)の遺留分は1/3になります。
遺留分計算の基になる「相続財産」は民法で以下のように規定されています。
民法1043条:「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」
条文に照らした計算式は以下のようになります。
相続財産=被相続人の財産+贈与した財産(1年以内の第三者への贈与+10年以内の相続人への贈与)-債務(借金等)
相続分の指定と遺留分
遺言書で各相続人に相続分を割り当てることを、遺産分割方法の指定と言います。
「甲土地を長男Aに相続させる」というように、相続財産を指定して特定の相続人が相続できるように遺言書に記載します。
甲不動産はAに、乙不動産はBに、その他の不動産はCに、預貯金はD、Eに各1/2ずつ等々、自由に指定できます。
また、「次男Bには何らの財産も相続させない」と記載することも可能です。
このように指定するのは自由なんですが、問題になるのが遺留分です。
遺産分割の指定によって相続人の相続分が遺留分より下回ってしまうと、問題になる可能性が出てきます。
遺留分を下回っている相続人、相続させないとされた相続人が自己の遺留分を主張したら、他の相続人は拒否することはできません。
自分たちの相続分から、または自分自身の財産から遺留分相当額を金銭で渡さなければいけなくなります。
相続財産の大部分が不動産で、相続した相続人自身に遺留分に相当する金銭財産がなければ、相続した不動産を売却してそこから遺留分相当額を支払うことになってしまいます。
また、相続人が複数人いれば、遺留分者以外の相続人が遺留分を負担することになります。
相続人A、B、C、DでDが遺留分を請求した場合、ABCでDの遺留分を負担することになりますが、誰がどれだけ負担するかでもめるおそれもあります。
こうならないように、遺留分を考慮した遺言書を作成することが重要になります。
遺留分を渡す遺言
遺言書で全相続人に対して最低でも遺留分相当の遺産分割指定をすることで、遺留分に関する紛争を回避できます。
各相続人の相続割合が不均衡でも、遺留分を超える分の請求は認められていないので、内容に不満があっても受け入れるほかなく、相続人が互いに争い合う事を防げます。
遺留分を留保しておく
前述したように遺留分は必ず渡さなければならないものではありません。
あくまでも、請求されたときに渡すものです。
そこで、遺言書には遺留分を考慮せずに思いの通りに各相続人に相続分を指定しておいて、同時に遺留分が請求されたときに相当額を誰が、どう支払うかを指定しておく、という方法があります。
例えば、相続人が子3人で
1項.甲不動産を長女Aに相続させる。
2項.その他の不動産を含む一切の財産を長男Bに相続させる。
3項.次男Cには一切の財産を相続させない。
とする遺言書の場合、相続が発生し遺言書の通り相続手続きをしたとき、次男Cが何も請求しなければ問題ありませんが、Cが遺留分である相続財産の6分の1を請求したらABで遺留分相当額の金銭を準備して渡さなければいけません。
そこで、4項で「遺留分侵害額の請求は長男Bが負担するものとする。」と記載して、BにはCが遺留分を請求した場合を想定して現金・預貯金を多めに指定したりします。
遺留分相当額を金銭で指定できないようであれば、生命保険金の受取人にして保険金を遺留分相当額に充当できるようにしておくこともできます。
※基本的に生命保険金は相続財産の対象になりません(相続税の対象にはなります)。
このように、相続させない相続人や遺留分を下回る相続人から遺留分を請求されても他の相続人が困らないように、また対処でもめないように指定しておくことが重要です。
まとめ
折角残した遺言書が揉め事の原因になっては何の意味もありません。
遺言書は形式と同様に内容も重要です。
残された家族が自分が残した遺産で仲たがいすることは悲しいことですが、多いことも事実です。
遺言書は単に書けば良いというものではありません。
遺留分も含めて書く内容を考慮し、もめない遺言書を残すことが大事です。
内容にご不安はある方は、当事務所の遺言書作成サポートをご利用下さい。
初回相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご連絡下さい。
ご相談は事前にご予約下さい。土、日、祝日や仕事終わりの夜(20時まで)のご相談も対応可能です。